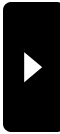2015年08月08日
本で使う図版は、レイアウトの引き出しを増やせ
本を執筆する場合、著者が基本的に図版の指示をします。
これ、慣れてないと、なかなか大変な作業です。
文章を図で表現するわけですからね。
しかも、似たようなパターンは何度も使えないという…。
何かを文章で説明するのは、話しでコミュニケーションをとってる我々には、それほど難しい問題ではありません。
しかし、それをビジュアルで説明するわけですから、何をどうすればいいんだか…って感じです。
でも、図版は慣れです。
図版のバリエーションをサンプルとして知っていれば、どういう説明の場合にどういう図版を使えばいいのかが分かります。
そのためにも、事前に図版のバリエーションをいっぱい確保して、それを引き出しにしておくことをオススメしています。
今回、弊社でプロデュースした、あーや先生の『売れっ子ハンドメイド作家になる本』は、そういう意味では、右が文章、左が図版という構成になっていますので、図版のバリエーションを勉強するのには最適な一冊となっております。
著者のあーや先生が苦労して考え尽くして作った図版を、労せず、自分の引き出しに使えるなんて、これほど楽なことはありません。
いずれ出版したいと思っているのであれば、是非、この本を手元に置いておきましょう。
そうすることで、図版の苦労は半減しますからね。
売れっ子ハンドメイド作家になる本
http://www.amazon.co.jp/dp/4883379949
これ、慣れてないと、なかなか大変な作業です。
文章を図で表現するわけですからね。
しかも、似たようなパターンは何度も使えないという…。
何かを文章で説明するのは、話しでコミュニケーションをとってる我々には、それほど難しい問題ではありません。
しかし、それをビジュアルで説明するわけですから、何をどうすればいいんだか…って感じです。
でも、図版は慣れです。
図版のバリエーションをサンプルとして知っていれば、どういう説明の場合にどういう図版を使えばいいのかが分かります。
そのためにも、事前に図版のバリエーションをいっぱい確保して、それを引き出しにしておくことをオススメしています。
今回、弊社でプロデュースした、あーや先生の『売れっ子ハンドメイド作家になる本』は、そういう意味では、右が文章、左が図版という構成になっていますので、図版のバリエーションを勉強するのには最適な一冊となっております。
著者のあーや先生が苦労して考え尽くして作った図版を、労せず、自分の引き出しに使えるなんて、これほど楽なことはありません。
いずれ出版したいと思っているのであれば、是非、この本を手元に置いておきましょう。
そうすることで、図版の苦労は半減しますからね。
売れっ子ハンドメイド作家になる本
http://www.amazon.co.jp/dp/4883379949
2015年07月16日
原稿で編集者を唸らせろ!
編集者は、日夜、本を作っています。
出版社や編集部によっては、ジャンルが固定されている場合も少なくありません。
ということは、同じジャンルの似たようなテーマで何冊も本を作ることもしばしば…。
実際に、私もアフィリエイト、、Facebook、アメブロ、LINE、iPhone、スマホの本に関しては、日本一の冊数を制作しています。
もちろん、切り口は全部違います。
でも、同じテーマで本を作り続けていると、たまに思うことがあるんです。
「これ以上の本は作れないかも…」
そう思ってしまったら、もうそのテーマでは本は作りたくなくなるんです。
だって、過去に作った自分の本より、もっといい本を作れる自信がないから…。
その時、自分の中で最高だと思えない本は、やっぱり出したくないと思うのは、編集者心理というものです。
どうせ、出版を目指すなら、それぐらいのクオリティを目指しましょう。
編集者と話し、読者を見据えて、最高の本を作ってください。
そうすると、編集者は唸ります。
そして、もう二度とそのテーマでは本は作りたくなくりますから。
今回のブログ本は、私にとってそういう本に仕上がりました。
もうよほどのノウハウがない限り、ブログ本は作らないと思います。
ブログの必要性を感じている人は、絶対に読んで欲しいです。
今なら、購入特典がもらえるアマゾンキャンペーン中ですよ。
http://mutomasataka.com/blogwriting/
出版社や編集部によっては、ジャンルが固定されている場合も少なくありません。
ということは、同じジャンルの似たようなテーマで何冊も本を作ることもしばしば…。
実際に、私もアフィリエイト、、Facebook、アメブロ、LINE、iPhone、スマホの本に関しては、日本一の冊数を制作しています。
もちろん、切り口は全部違います。
でも、同じテーマで本を作り続けていると、たまに思うことがあるんです。
「これ以上の本は作れないかも…」
そう思ってしまったら、もうそのテーマでは本は作りたくなくなるんです。
だって、過去に作った自分の本より、もっといい本を作れる自信がないから…。
その時、自分の中で最高だと思えない本は、やっぱり出したくないと思うのは、編集者心理というものです。
どうせ、出版を目指すなら、それぐらいのクオリティを目指しましょう。
編集者と話し、読者を見据えて、最高の本を作ってください。
そうすると、編集者は唸ります。
そして、もう二度とそのテーマでは本は作りたくなくりますから。
今回のブログ本は、私にとってそういう本に仕上がりました。
もうよほどのノウハウがない限り、ブログ本は作らないと思います。
ブログの必要性を感じている人は、絶対に読んで欲しいです。
今なら、購入特典がもらえるアマゾンキャンペーン中ですよ。
http://mutomasataka.com/blogwriting/
2015年07月13日
出版が決まったのに、本の原稿が書けない!
本の原稿は、だいたい10万文字と言われています。
この10万文字の文字数をどれだけの人がイメージできているでしょうか?
ブログのノウハウ記事が、だいたい600文字から800文字なので、125~165記事ぐらいです。
しかも、ブログと違って、ひと記事完結ではなく、一冊完結という大きな流れを作らなくてはいけません。
では、書けない人の特徴を考えてみます。
最初は、そもそも文章が書けないという人。
こういう方は、「そもそも、なんで出版したいって思ったの?」って思ってしまいますが、非常に多いですね。
日常的に使っている日本語だからと軽く考えているんでしょうね。
でも、文字だけで何かを説明をする難しさというのは、会話とは違います。
いくら日常的に使っている日本語だといっても、文字で説明する練習をしていないとなかなか難しいですね。
そういう人は、まずはブログを始めましょう。
次に多いのが、文章は書くけど、日本語ではない場合。
日本の文字を使っているのですが、何が書かれているか、全く分からない状態です。
これは、人に読ませる、人に理解させるという思考がない人に多い傾向です。
こういう人は、実名でどんどんブログで文章を書いてください。
公開された場で、読者を想定して、何かを伝えるノウハウ記事を書くことで、書き慣れます。
人に説明するのに必要な論理展開などが自然と身につくでしょう。
最後は、大きな流れを作れない人。
ブログの記事は書けても、その記事をつなげて大きなひとつの何かノウハウを説明することができないという状態です。
こういう人は、自分のノウハウを徹底的にかみ砕いて、目次案に落とし込む必要があります。
全体を俯瞰しながら、どこで何を説明するべきなのかを考えるのです。
セミナーでスライドの順番を決めるのと同じだと思ってください。
いきなり文章を書くことを考えるのではなく、章、節、項(見出)の階層までを、足したり、引いたり、入れ替えたりしながら先に決めるんです。
そしたら、あとはブログ記事を書くのと一緒ですからね。
つまり、本のタイトルをブログタイトルにして、章をブログのカテゴリー、節タイトルを記事タイトルにして、どんどん書くイメージです。
あとは、その記事をプリントアウトして並べ、話しのおかしい部分を直したり、記事を追加していく。
そうすることで、書籍を想定した文章の練習ができますからね。
かつて、出版を実現された彼女は、最初から出版を意識してブログをやってました。
http://ameblo.jp/amecustom/entry-10349372895.html
本の目次チックのカテゴリー分けになってますよね。
出版が決まったのに、本の原稿が書けない!と悩まないように、最初から出版を意識してブログをやるようにしてください。
それだけで、全く変わってきますから。
この10万文字の文字数をどれだけの人がイメージできているでしょうか?
ブログのノウハウ記事が、だいたい600文字から800文字なので、125~165記事ぐらいです。
しかも、ブログと違って、ひと記事完結ではなく、一冊完結という大きな流れを作らなくてはいけません。
では、書けない人の特徴を考えてみます。
最初は、そもそも文章が書けないという人。
こういう方は、「そもそも、なんで出版したいって思ったの?」って思ってしまいますが、非常に多いですね。
日常的に使っている日本語だからと軽く考えているんでしょうね。
でも、文字だけで何かを説明をする難しさというのは、会話とは違います。
いくら日常的に使っている日本語だといっても、文字で説明する練習をしていないとなかなか難しいですね。
そういう人は、まずはブログを始めましょう。
次に多いのが、文章は書くけど、日本語ではない場合。
日本の文字を使っているのですが、何が書かれているか、全く分からない状態です。
これは、人に読ませる、人に理解させるという思考がない人に多い傾向です。
こういう人は、実名でどんどんブログで文章を書いてください。
公開された場で、読者を想定して、何かを伝えるノウハウ記事を書くことで、書き慣れます。
人に説明するのに必要な論理展開などが自然と身につくでしょう。
最後は、大きな流れを作れない人。
ブログの記事は書けても、その記事をつなげて大きなひとつの何かノウハウを説明することができないという状態です。
こういう人は、自分のノウハウを徹底的にかみ砕いて、目次案に落とし込む必要があります。
全体を俯瞰しながら、どこで何を説明するべきなのかを考えるのです。
セミナーでスライドの順番を決めるのと同じだと思ってください。
いきなり文章を書くことを考えるのではなく、章、節、項(見出)の階層までを、足したり、引いたり、入れ替えたりしながら先に決めるんです。
そしたら、あとはブログ記事を書くのと一緒ですからね。
つまり、本のタイトルをブログタイトルにして、章をブログのカテゴリー、節タイトルを記事タイトルにして、どんどん書くイメージです。
あとは、その記事をプリントアウトして並べ、話しのおかしい部分を直したり、記事を追加していく。
そうすることで、書籍を想定した文章の練習ができますからね。
かつて、出版を実現された彼女は、最初から出版を意識してブログをやってました。
http://ameblo.jp/amecustom/entry-10349372895.html
本の目次チックのカテゴリー分けになってますよね。
出版が決まったのに、本の原稿が書けない!と悩まないように、最初から出版を意識してブログをやるようにしてください。
それだけで、全く変わってきますから。